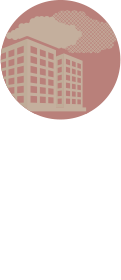池泉回遊式庭園が見どころの「北園」【2025/06更新記事あり】

揚輝荘は素晴らしい庭園も見どころのひとつ。ここでは京都の修学院離宮を参考にした池泉回遊式庭園がある北園について詳しく紹介していきます。
無料で楽しめる
揚輝荘は一般公開されていますが、北園は無料で解放されているので特に申し込みをしなくても素敵な庭園を見ることができるんです。春には満開に咲き誇る桜や宙にたゆたう姿が美しい藤を眺めたり、初夏にはきらめく若葉を見ながらお散歩したり、秋には赤や黄色に色づく紅葉を愛でたり、と四季折々の花々を楽しめますよ。
北園のシンボル「白雲橋」
北園は真ん中に池がありその周りをぐるっと回りながら鑑賞できる池泉式遊式庭園になっています。その池には北園のシンボルでもある白雲橋がかかっていますが、京都にある修学院離宮の千歳橋をなぞらえて作られたといわれています。屋根のある珍しい橋ですが、残念ながら有形文化財に指定されているため実際に渡ることはできません。
天井に描かれている龍の絵や手掘りの白木擬宝珠など見どころが満載の白雲橋では橋の上を舞台にして音楽や踊りを楽しむイベントも開催されています。
徳川家に縁のある建物「伴華楼」
伴華楼と書いて「ばんかろう」と読む建物は1929年に尾張徳川家から移築された座敷に洋室などを増築した建物です。近代建築の巨匠といわれている鈴木禎次が設計しました。伴華楼は英語のバンガローをもじってつけられたのだとか。祐民のちゃめっ気のある性格が反映されていますね。
伴華楼は一般公開されているので予約すれば無料で内部を見学することができます。豊富な知識を持ったスタッフが装飾など詳しく教えてくれるので安心して楽しむことができますよ。公開日は水曜日と土曜日で1日4回行われていますが、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために公開を中止している場合もあります。事前に見学できるかどうか電話で確認しておきましょう。
企業の繁栄を願う「豊彦稲荷」
伴華楼を進んでいくと、緑の木々の中に朱塗りの鳥居がぱっと目に入ってきます。こちらは松坂屋名古屋店本館と大阪にある高槻店にも鎮座している豊彦稲荷で、昭和初期に松坂屋京都店から勧請されたのだとか。お稲荷さんなので入口には凛々しいお顔の狐さんも鎮座しています。お散歩の際にお参りしてみてはいかがでしょうか?
最初に建てられた「三賞亭」
池に面している三賞亭は揚輝荘最初の建物です。雪・花・月を鑑賞するための建物なので「三賞亭」と名付けられたようです。 木造の平屋建てで障子戸を開けると池と白雲橋がちょうどよく眺められるようになっています。建物内には桜や新緑、紅葉など四季の移り変わりを楽しめる茶室もあり、現在も茶会が開かれているようですよ。
植栽が語る、北園の知恵と四季の表情(2025年6月25日追記)
揚輝荘北園は、庭園だけでなく植物の配置にも深い意図が込められた空間です。ここでは、四季を豊かに彩る植栽の工夫によって、もてなしと自然観が見事に融合しています。
まず注目したいのは、シャシャンボ(藪柑子)です。本州以西を原産とする常緑低木で、北園にはたくさん植えられています。春に白い小花を咲かせ、秋には食べられる赤い実をつけるその様子は、訪れた人に季節の移ろいを自然に感じさせてくれます。
地被植物では、ジャノヒゲやヤブランが庭園の足元をしっとりと彩り、斜面の崩れを防ぎながら控えめな美しさを添えています。とくにジャノヒゲは、法面の補強(根締め)にも活用され、見た目以上に実用的な役割を果たしているのが庭師の知恵です。
また、苔類にも計画的な植栽がされており、コケの中でもコバノチョウチンゴケやナガヒツジゴケなど5種が重視されて保育されています。これによって、湿潤な環境に適した地表が保たれ、北園全体が落ち着いた佇まいを維持しています。
さらに、サギソウやシャガといった植物は、水辺や日陰地に調和し、自然湧水の水脈を活かした植え込みが見事です。サギソウは湿性環境を好むラン科の多年草で、その繊細な白い花姿はまるで空を飛ぶサギのよう。シャガは中国原産で群生しやすく、雑草防止にも役立つとともに、庭に上品な花を添えます。
こうした植栽の組み合わせは、北園を単なる観賞用ではなく、「歩きながら四季を感じ、自然のリズムを感じる場」にしているのが特徴。揚輝荘北園を訪れた際は、ぜひ足元の植物や苔、小道脇の花たちにも目を向けてみてください。そこには、庭師のもてなしの心と、自然を敬う知恵がしっかり息づいています。